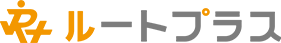運動能力は伸びたほうがいい!
これは誰もが共感し、そうなればいいなと考えることでしょう。
では、どうすればいいのか?
ズバリ、運動能力を伸ばすために必要なことは習慣をつけることです。
今回は運動能力を伸ばすための習慣をまとめます!
①失敗しても子どもがチャレンジしたことをほめる。
まずは運動にチャレンジしたこと自体を褒めましょう。
苦手なところから一歩踏み出すことが大切です。
②なるべく、たくさんのスポーツにふれさせてあげる
こどもがなにをすきになるかわからないからこそ
たくさんのスポーツを触れる機会をつくりたいですね。
スポーツを習慣化するヒントが隠されていることでしょう。
③少しでも毎日運動を続ける。
一緒に散歩をする、少し公園で遊ぶなど
運動に対して一緒に取り組んであげることが大切です。
そして毎日積み重ねることが運動を習慣化することに繋がります。
このように子どもたちの目線に寄り添いながらも
私たち大人がサポートして導いてあげましょう。
未来を担う子どもたちが運動を通してより豊かになることを願っています。
代表 伊藤一哉