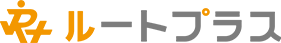昔は外遊びもたくさん行われており
近所の《お兄さんや少し上の学年のお兄さん・お姉さん》とも
たくさんの交流がありましたね。
現代では”核家族化や公園への規制„など
様々な要因により、遊びの機会が消失しています。
遊びの良さは、もちろん《体を動かすことや工夫をして取り組むこと》で
新たなアイデアが生まれることも魅力の一つですが。
学年関係なく、楽しめることも魅力的でした。
こういった異学年交流を通して、上級生はリーダーシップを学び
下級生は「あんな風になりたいな」という憧れをもつでしょう。
そして遊び感覚だからこそ、コミュニケーションも活発になります。
このような環境で子どもたちが伸び伸びと成長していく環境を創れるように
私たち大人も協力し合いながら、子どもたち一人ひとりに関わっていきましょう
代表 伊藤一哉