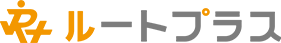子育ての悩みの一つに「みんなと一緒に取り組めない」「協調性がないと感じる」ことがあるのではないでしょうか。
例えば保育園や幼稚園での活動では日常の活動に体操やリズム運動が取り入れられていることも多く、運動会が近づけば器械運動やかけっこが行われることもあります。
子ども自身の興味とは関係なく、《皆と一緒に取り組む運動》を、本人がやりたくないというときは、どう対応するのが望ましいでしょうか。
私は、まず”本人に気持ちを聞く”のが大切だと考えています。
例えばリズム運動の場合、《本質は皆と合わせて上手に踊ることではなく、リズムに合わせて体を動かすこと》です。
そのため、一律にやらせようとしなくてもいいのではないでしょうか。
大切なことは、本人の気持ちを聴いてあげることです。
本人に”なぜやらないのか”気持ちを聴いてみて「みんなを見ているのが楽しい」というなら
「じゃあ音楽を聴いて手だけ叩いてみよう」とアプローチをしてみると、だんだん体を動かし始めるかもしれません。
保育園で流れるリズム運動用の曲が好きではないというなら、自宅でアンパンマンの曲をかけてみてもいいでしょう。
その子の興味を引き出してあげることが大切だと思います。
親は家庭で子どもの気持ちに耳を頼け、無理のない範囲で体を動かせるよう、前向きな気持ちをつくってあげるのが大切です。
無理をさせないことと甘やかすことはまた違いますが
前提として《子どもの声を聴いてあげる、寄り添ってあげること》が必要です。
周りを見て自分の子を見るのではなく、その子自身の特徴、良さを見てあげましょう。
代表 伊藤一哉